「都道府県かるた」は家にあるけどそんなに出番がない…。
もう飽きちゃって子どもも食いついてこない…。
そんなことありませんか?

かるたばっかりは飽きるわ〜。
この記事では、都道府県かるたの応用編「特産品や県の特徴まで覚えられちゃう遊び方」をお伝えします。
「お勉強」ではなく「遊ぶ」ために都道府県の特徴を覚えることができますよ。
場所を変えるだけで新しい遊びになります
まず遊ぶ場所をリビングからお風呂場に移して、湯船に浮かべます。
「かるた濡らしてもエエのん!?」と思った方、ご安心ください(笑)。
耐水性のカードにする方法は別の記事にします。
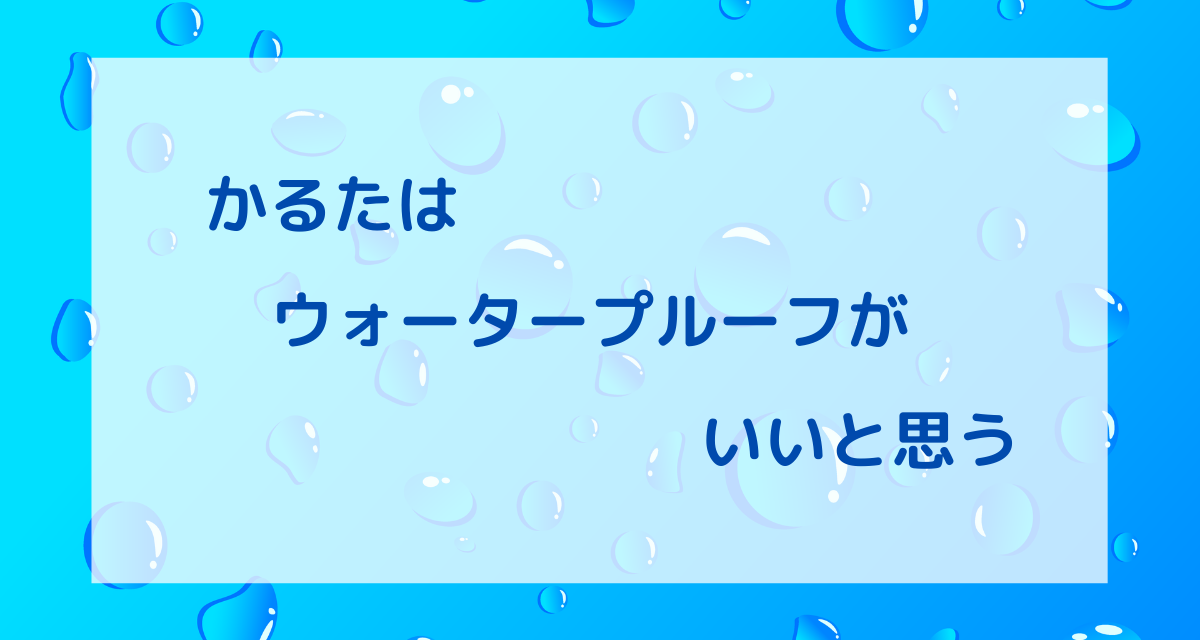
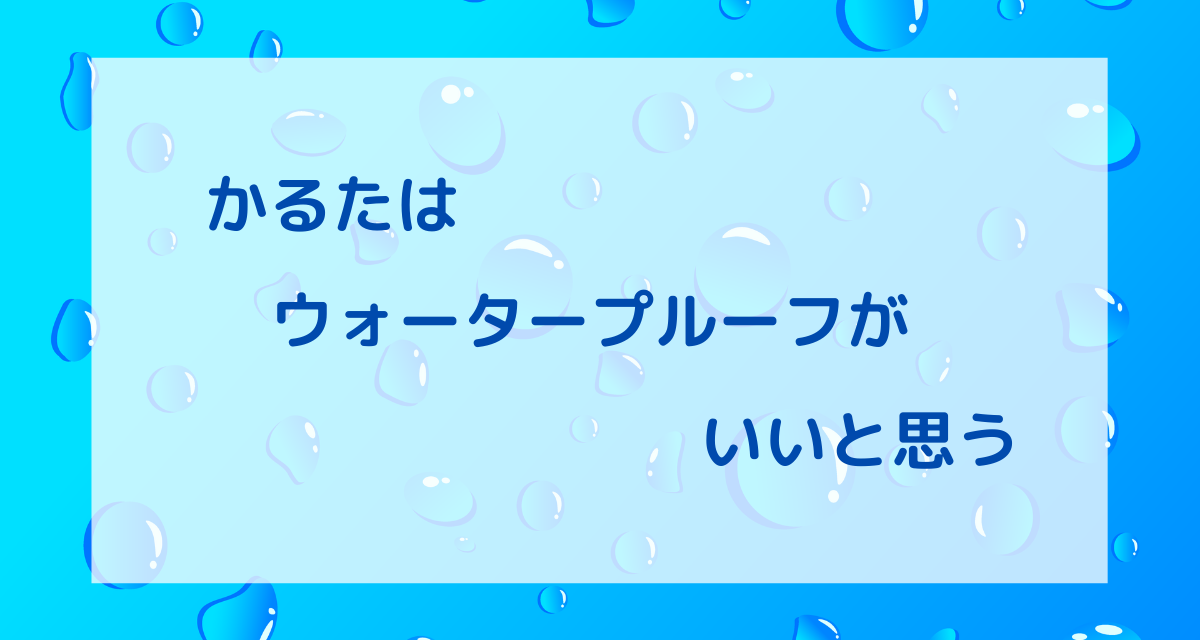
もうね、「お風呂になんか浮かんでる」これだけで子どもって喜びます。
しかもお風呂場って他に入ってくる情報が少ないので、リビングよりも気が散らずに都道府県で盛り上がれるんですよ。
まずは「これは何県?」
使うのは絵札(取り札)のみ。最初は、目に入った一枚をとって「これは何県かな?」とクイズを出してみましょう。
まだ都道府県の概念がない未就学児さんは、「なんて書いてある?」と県の名前を読んでもらうとよいと思います。
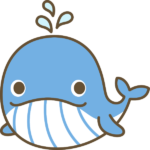
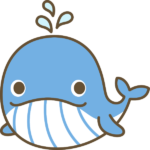
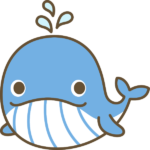
やまがたけん!
最初は県名に関心を持ってもらえたら十分です。



まずは嫌いにならない、好きになってもらえたらラッキー!
特産品でクイズを出す
都道府県になじんできたところで、次は特産品でクイズを出します。



「梅」がよく取れる県はどーこだ?
ここで、「梅」というキーワードと和歌山県が結びつきます。思いつくものや目についたものからクイズにしていきましょう。
これもあまりしつこく重くならないよう、一緒に「楽しむ」ことを忘れないでくださいね。お子様にクイズを出してもらうのもよいと思います。
「もっとクイズ出してほしそうだな」とか「そろそろ飽きてきたかな」とか
お子様が出す雰囲気を見てあげましょう。
無理強いすると、子どもは「都道府県は嫌なもの」という印象をもってしまいます。
思い出の場所クイズを出す
特産品に飽きてきたら、家族旅行などで訪れた土地やゆかりのある土地を探してみましょう。
そこで食べたものや見に行ったものの思い出話をするのも楽しいですよ。
壁にペタペタ貼って楽しむ
最後は好きなように遊んでもらいましょう。
我が家の場合はお風呂の壁にペタペタ貼って遊んでいました。
何が楽しいのか…未だによく分かりませんが、楽しんでくれているようです。
注意点
ただ、注意した方がよいことが1点。



47枚全部入れると湯船がカオスになります。
カードが多すぎると、その多さに注意が向けられてしまって各県の情報が頭に入ってきません。
しかもカードが重なるので「何県のカードがどこにある」とかもう探す気になれません(笑)
いやこれはホント大変でした。片付けもね。
1回のお風呂タイムに入れるのは1地方だけにしましょう。
まとめ
最後までお読みいただきありがとうございます。
お風呂で楽しむ都道府県カードゲーム、いかがでしたか?
それではまとめです。
- 絵札の中から1つの地方を選んで湯船に浮かべる
- まずは県名をクイズに出す
- 特産品や思い出の場所クイズを出す
- 最後は好きに遊んでもらう
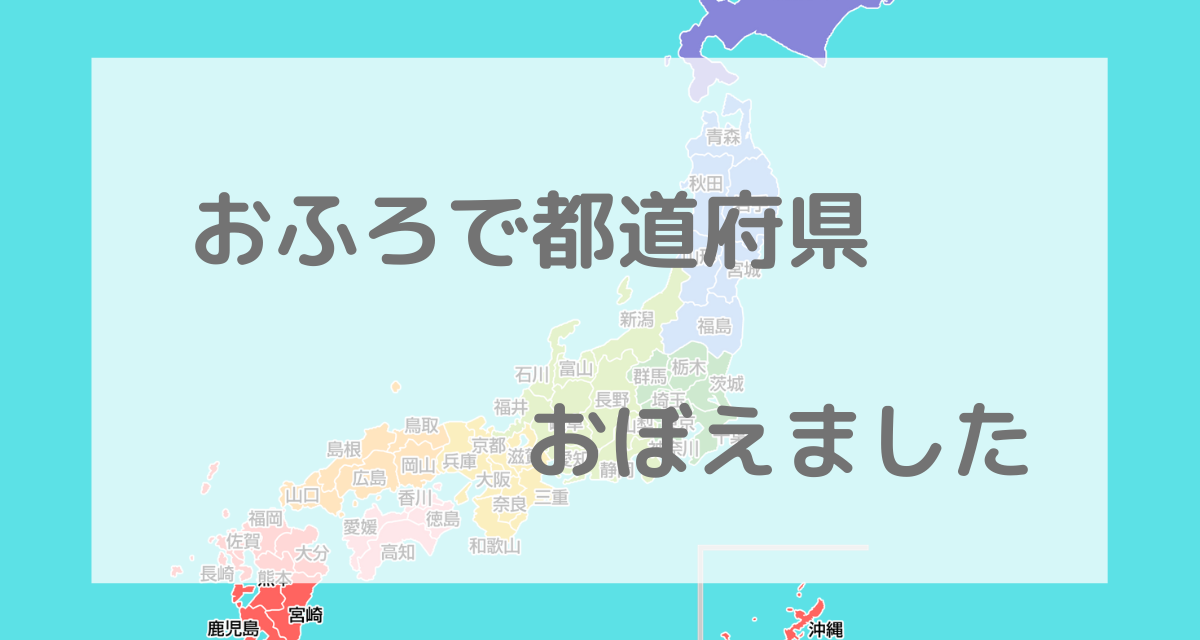
コメント